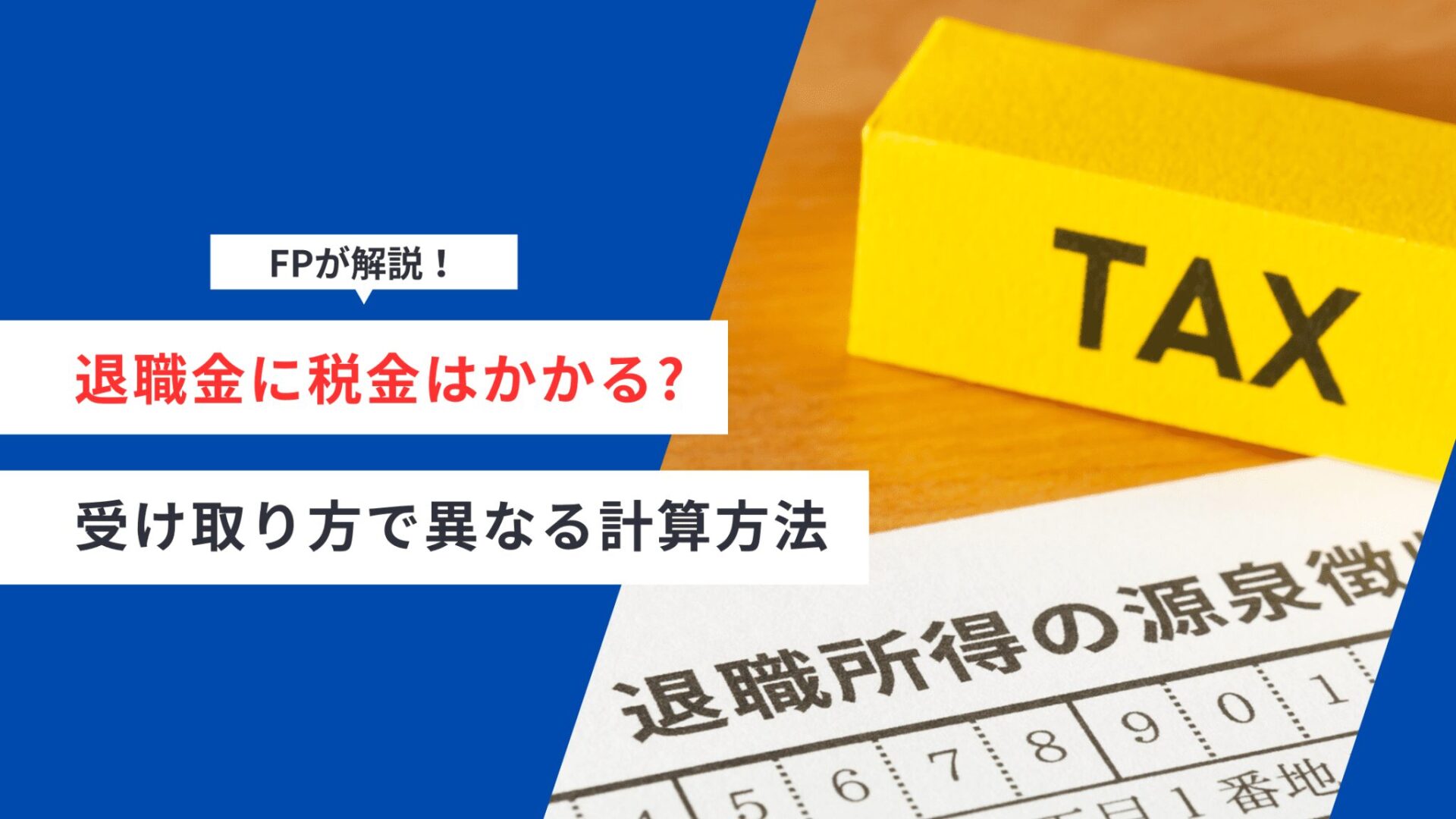退職金を受け取るとき、「どのような税金がいくらかかるのかわからない」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。
退職金とは、企業が退職する従業員に対して、労働の対価として支給する報酬です。老後資金として重要な資産であり、会社の規模や勤続年数などで支給額が異なります。
また、退職金には特別な控除制度が設けられており、正しい知識を身につければ、税負担を抑えることが可能です。
本記事では、退職金にかかる3つの税金や計算方法、受け取り方による違い、確定申告が必要なケースについて詳しく解説します。最後まで読めば、退職金を賢く受け取るための具体的な判断ができるようになります。
退職金に税金がかからないこともある?

通常、退職金には税金がかかります。ただし、退職金の額面が退職所得控除額より少なければ、税金は発生しません。
退職所得控除額は、退職金にかかる税額を計算する過程で、勤続年数に応じて決まる控除額です。
勤続年数に応じた退職所得控除額の具体的な数値を、下表にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 1年 | 80万円 |
| 2年 | 80万円 |
| 3年 | 120万円 |
| 4年 | 160万円 |
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
出典:国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
退職金から控除額を差し引けるため、退職金にかかる税負担を軽減できます。つまり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、税負担が軽減される仕組みです。
退職金にかかる3つの税金
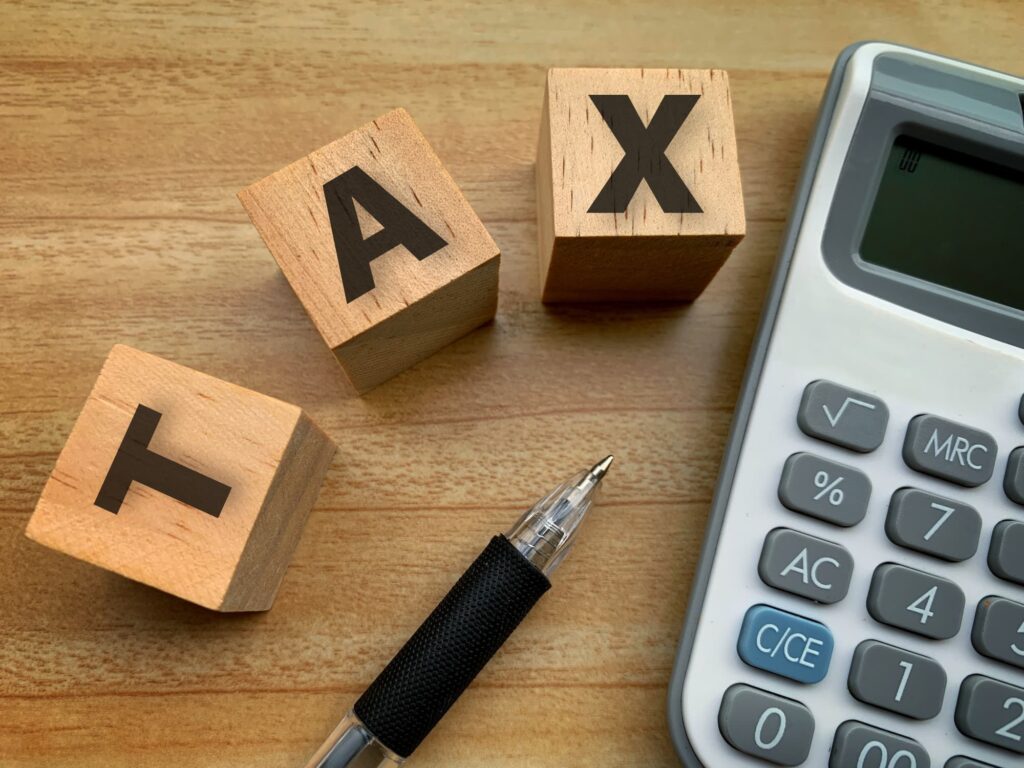
退職金にかかる3種類の税金は、以下のとおりです。
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税
各税金の概要や計算方法を解説します。
所得税
所得税とは、個人が得た所得に対して課される税金です。
1月1日から12月31日までの年間所得から、各種の所得控除を差し引いた課税所得に基づいて計算されます。
計算式は、以下のとおりです。
所得税 = 課税所得 × 税率 − 税額控除額
所得税では累進課税制度が採用されており、所得が増えるにつれて税率が段階的に高くなります。
課税所得金額に応じた税率・控除額は、以下のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
住民税
住民税とは、毎年1月1日時点で住んでいる自治体に納める地方税です。前年の1月から12月までに得た所得に対して課税されます。
住民税の税額は、「均等割」と「所得割」を合算した金額です。
均等割:所得に関係なく一律5,000円
所得割:前年の課税所得に一律10%
基本的に、均等割は、所得に関係なく一律5,000円が課されます(市区町村民税3,000円、道府県民税1,000円、森林環境税1,000円)。
一方で、所得割は前年の所得に応じて課され、税率は一律10%です(市区町村民税6%、道府県民税4%)。
復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興の財源確保として導入された税金です。
所得税に上乗せされて課税される「付加税」として、基準所得税額の2.1%が課税されます。2013年から2037年までが課税対象期間です。
退職金にかかる税金の計算方法

退職金は、受け取り方で、課税方法や適用可能な控除、税額が異なります。退職金の受け取り方は、以下の3パターンです。
- 一時金で受け取る場合
- 年金で受け取る場合
- 一時金と年金を併用して受け取る場合
退職金の受け取り方を指定している企業もあるため、勤務先で可能な受け取り方を確認しておきましょう。
一時金で受け取る場合
退職金を一時金として受け取る場合、退職所得は「分離課税」の対象となります。分離課税とは、他の所得と切り離して税金を計算する課税方法です。
一時金で受け取れば、退職所得控除が適用されます。退職所得の計算式は、以下のとおりです。
退職所得 = (収入金額 – 退職所得控除額) × 1/2
退職所得控除は、以下のように、勤続年数によって計算方法が異なります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(ただし、80万円未満の場合は一律80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
出典:国税庁|退職金と税
退職所得控除額が大きくなることで、課税所得の金額を抑えられ、税制上有利になるケースが少なくありません。そのため、退職所得控除を利用できる一時金で受け取れば、同額の退職金でも、手元に多くの資金を残せる可能性があります。
年金で受け取る場合
退職金を年金として受け取る場合、雑所得として扱われます。一時金とは異なり、退職所得ではないため、退職所得控除は適用されません。
また、年金として受け取る退職金は総合課税の対象となり、公的年金や企業年金など他の雑所得と合算して課税されます。雑所得は以下の計算式で算出されます。
雑所得 = 収入金額 – 公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が年間1,000万円以下の場合、公的年金等控除額は以下のとおりです。
| 年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超〜130万円未満 | 60万円 | |
| 130万円以上〜410万円未満 | 収入金額 × 0.75 – 27万5,000円 | |
| 410万円以上〜770万円未満 | 収入金額 × 0.85 – 68万5,000円 | |
| 770万円以上〜1,000万円未満 | 収入金額 × 0.95 – 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額 – 195万5,000円 | |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超〜330万円未満 | 110万円 | |
| 330万円以上〜410万円未満 | 収入金額 × 0.75 – 27万5,000円 | |
| 410万円以上〜770万円未満 | 収入金額 × 0.85 – 68万5,000円 | |
| 770万円以上〜1,000万円未満 | 収入金額 × 0.95 – 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額 – 195万5,000円 |
企業が退職金を運用し続けることで運用益が加わり、将来的な受取総額が増える可能性があります。一方で、退職所得控除が適用されないため、控除額が小さくなり、税制面では不利になることがある点には注意しましょう。
一時金と年金を併用して受け取る場合
退職金を一時金と年金の両方で受け取れるケースもあります。
一時金として受け取る分は、退職所得として分離課税となり、退職所得控除が利用可能です。一方で、年金として受け取る分は、雑所得として総合課税となり、公的年金等控除が適用されます。
退職金の金額が退職所得控除額を超える場合でも、両方の控除を活用すれば、税負担を抑えられる可能性があります。
また、住宅ローンや教育費などのまとまった資金が必要な分は一時金で、残りを年金で受け取ることで、計画的な資金管理が可能です。
ただし、受け取る金額や割合で、税金や社会保険料の金額が大きく変わることもあります。そのため、専門家へ相談のもと、事前にシミュレーションすると良いでしょう。
退職金にかかる税金の計算シミュレーション

ここでは、退職金にかかる所得税を具体例を交えて計算します。勤続年数と退職金額が異なる2つのケースでシミュレーションしてみましょう。
【ケース1】勤続年数11年・退職金支給額1,000万円の場合
勤続年数が20年以下であるため、退職所得控除額は440万円、課税所得は280万円です。
退職所得控除:40万円 × 11年 = 440万円
課税退職所得:(1,000万円 – 440万円) × 1/2 = 280万円
国税庁の「所得税の速算表」より、課税退職所得が280万円の場合、税率10%、控除額9万7,500円であるとわかります。所得税と復興特別所得税額を計算すると、以下のとおりです。
所得税:280万円 × 10% − 9万7,500円 = 18万2,500円
復興特別所得税額:18万2,500円 × 2.1% = 3,832円(端数は切り捨て)
このように、勤続年数11年・退職金支給額1,000万円の場合、所得税と復興特別所得税額は合計18万6,332円かかります。
【ケース2】勤続年数25年・退職金支給額3,000万円の場合
勤続年数が20年以下であるため、退職所得控除額は1,150万円、課税所得は925万円です。
退職所得控除:800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円
課税退職所得:(3,000万円 – 1,150万円) × 1/2 = 925万円
国税庁の「所得税の速算表」より、課税退職所得が280万円の場合、税率10%、控除額9万7,500円であるとわかります。所得税と復興特別所得税額を計算すると、以下のとおりです。
所得税:925万円 × 33% − 153万6,000円 = 151万6,500円
復興特別所得税額:151万6,500円 × 2.1% = 31,846円(端数は切り捨て)
このように、勤続年数25年・退職金支給額3,000万円の場合、所得税と復興特別所得税額は合計154万円8,346円かかります。
退職金を受け取るときに確定申告は必要?

原則、退職金にかかる税金は会社が源泉徴収してくれるため、確定申告をする必要はありません。ただし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。
申告書を提出することで、退職所得控除が適用され、税額が軽減されます。申告書を提出しなければ、退職金に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されるため、税負担が大きくなる可能性があります。
また、退職金の申告書を提出しても、医療費控除や寄附金控除などの所得控除を受けたい場合は、確定申告しましょう。
【FPの見解】今後は退職金への課税が強化される可能性がある!?

退職金にかかる税金は、勤続年数が長いほど優遇される仕組みです。しかし、終身雇用を前提とした旧来型の優遇が、現代の多様な働き方や労働市場の流動性に合っていないため、見直しが必要とされています。
2025年度の税制改正では、退職金に対する課税制度の抜本的な見直しは見送られました。政府は、具体的な結論を出さず、議論を継続する方針です。
石破首相も2025年3月の国会で「拙速にはしないが、慎重に見直すべき」と述べており、変更を急がない姿勢を示しています。(※)そのため、2025年時点では現行制度が維持されており、増税されていません。ただし、2026年度以降の税制改正では再び退職金課税の見直しが議論される見通しです。
長期勤続者に対する優遇措置が縮小される可能性があり、将来的な課税強化が示唆されています。今後の動向には引き続き注視しましょう。
(※)出典:日本経済新聞|石破茂首相、退職金課税「適切な見直しを」
【まとめ】退職金にかかる税金を正しく理解し、賢く受け取ろう!
本記事では、退職金にかかる税金や計算方法、受け取り方による違い、確定申告の必要性について解説してきました。
退職金には、所得税・住民税・復興特別所得税の3つがかかります。ただし、退職所得控除や公的年金等控除の制度を活用すれば、税負担を軽くできる可能性があるため、正しい知識が欠かせません。
また、確定申告が必要になるケースもあるため、手続きにも注意が必要です。
今後、勤続年数で優遇される制度が見直される可能性もあるため、最新の情報には注視しておく必要があります。
退職金を有効活用するためにも、退職金にかかる税金を正しく理解し、自分に合った受け取り方を選択しましょう。